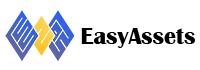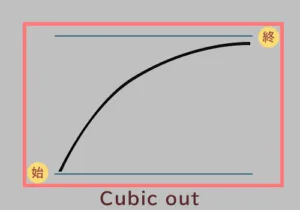失敗談から学ぶ!フォント制作に適したツール選び
掲載日: 2025/09/17 更新日: 2025/09/18
先日初めてオリジナルフォントを作りました!
完成したフォントが画面に表示された瞬間は、苦労が報われた喜びで小躍りしそうなくらい嬉しかったです。
ただ、制作中に思わぬ所でつまづき、必要以上に時間が掛かってしまいました。
この記事では、これからフォント制作に挑戦する方に向けて、
私の実体験をもとに「ツール選びの落とし穴」や「効率的な進め方」を紹介します。
特にこれから作る人には
「デザインツール選びは慎重に!!」
ということをお伝えしたいです。
■ツール選びで制作効率が変わる!
フォント制作初心者がまず知るべきことは
デザイン以降にどんな工程があるのか、どんなデータが必要なのか事前に把握することだと思います。
ただ絵を作って終わり!ではないので、各工程に進んでから「次は何か必要なんだろう?」と確認したのでは遅い場合があります。
まずは制作の全体像を把握してから、逆算して手段を選ぶことをおすすめします。
■フォント制作の全体フロー
まず前提として、フォント制作の流れを確認しましょう。
①フォントの仕様を決める(何文字作るか?スタイルの差分等)
②デザイン
③SVGデータとして書き出し※後述
④FontForgeでフォントとして登録・編集
⑤挙動確認
ここからは、各工程で注意したいポイントを解説します。
①フォントの仕様を決める(何文字作るか?スタイルの差分等)
→アルファベットと数字だけ?ひらがな、カタカナは作る?
→フォントはコンピューターに認識させるための「コード表」を基準に作るので
制作すべき文字・記号等を事前に把握しておきましょう
→太さのバリエーションを用意したい場合、細いverを基準に作成しましょう
FontForgeの標準機能に「輪郭を太らせる」機能があるので、後から調整可能なため
②デザイン
→最終的に必要なのはSVG形式のデータです。
SVG出力に対応しているツールか確認しましょう。
※pngとして書き出したデータをSVGに変換することも可能(後述)
③SVGデータとして書き出し
→FontForgeで細かい位置調整・形状の調整が可能なので「縦位置」だけ統一しましょう
④FontForgeでフォントとして登録・編集
→SVG形式のデータを一文字ずつ取り込み・登録します
⑤挙動確認
→Windowsの標準機能、MicroSoft製品、Adobe製品等、可能な限り様々なツールでデバッグしましょう。
私の場合、Microsoftの一部のツールのみで不具合が見つかりました。
■一番大変な工程:SVGデータの出力に注意!
実際に作ってみて一番苦労したのがSVG形式でのデータ出力でした。
デザインでも設計でもなくデータ出力?と思われるかもしれませんが
その原因は物量です。複雑で頭を使う作業より圧倒的な数の暴力に苦しめられました。
まず前提として、FontForgeに取り込むデータはSVG形式のデータでなければなりません。

・SVGとは
拡大/縮小してもデータが劣化しないベクター画像形式です。
解像度を損なわない編集が可能で、パスの編集データを保持した出力が可能。
・SVGデータの出力方法は大きく分けて2種類
①デザインツールから直接SVG形式を指定し出力する
②デザインツールからPNG等のラスターデータで出力し、外部ツールでSVGに変換する
※pngの内容物を輪郭検出し、自動でパスデータを作られます
自動検出なので、パス/アンカーが増えすぎて編集しづらいデータになる可能性あり
【私の制作手順】
①Adobe Photoshop(デザイン)
↓パスデータを保持したまま移植
②Adobe illustrator(SVGにデータ変換)
③FontForge(フォント登録・編集)
デザインツールにPhotoshop選んだのは、「あらゆる形式のデータに対応している」という思い込みと、慣れ親しんだツールであるという理由から。
ところがPhotoshopのSVG対応サポートが2024年に終了していたため
急遽SVGに変換する手段が必要になりました。
前述で「PNGをSVGに変換する方法もある」と記載しましたが
私の場合はもともとパスシェイプを使った制作を行っていたため、
pngとして出力した場合、その労力が無駄になってしまいます。
そのため、どうしてもパス情報を保持した状態でSVGで出力する必要がありました。
そこで、illustratorに同サイズのキャンバスを作り、作ったフォントのパスを一つずつコピーし、
1点ずつSVGとして出力する形で対応しました。
その手間およそ4時間。太い・細いver2種類分とはいえ、馬鹿にならない時間が掛かってしまいました。
最初からSVGに対応したツールで制作していれば変換の手間が大幅に削減できたと思います。
無料のツールでもSVGに対応&パスで制作できるものはあるので
これから始める方は、迷ったら下記のツールを使うことをおすすめします。
無料 → inkscape
有料 → Adobe illustrator
■まとめ
最初のツール選びが後の工程を左右する!
私のようにPhotoshopを使って後から変換に苦労するよりも、最初からSVGに強いツール(IllustratorやInkscape)を選んでおけば、時間も手間も大きく削減できました。
これから制作を始める方は、ぜひ「最終的に必要なデータ形式」から逆算して、ツール選びをしてみてください。
効率的なフォントライフを!